先日、観劇に行ってきました。

青年団プロデュース公演 尼崎市第7回『近松賞』受賞作品「馬留徳三郎の一日」
平田オリザさんが演出しているということを前日に知り、急遽行くことに決めました。
今年に入ってから演劇教育について調べたり勉強することが増えたのですが、平田オリザさんの記事や本をよく読んでいます。
その方とはピッコロ演劇学校に行っていた時に、特別講師としてきてくださった時に一度お会いしていましたが、こんなすごい演出家がいるんだ!と衝撃を受けたことを今でも覚えています。
実際に演出されている舞台を観たことなかったので、近くで公演するということもあり、これは観に行こう!と即決でした。
場所は懐かしのピッコロシアター。
一年しかお世話になりませんでしたが、良くも悪くも色んな思い出があります。笑
※以下、ネタバレ等も含まれます。
あらすじ
だまされたことさえ、
https://piccolo-theater.jp/event/16469/
忘れてしまえるなら……
山深い田舎の集落。
馬留徳三郎と妻のミネは二人でここに住んでいた。
ある夏の日、徳三郎の息子、雅文から久しぶりに電話がかかって来た。
仕事でトラブルがあり、部下が間もなく馬留家に訪れると言う――。
田舎の一軒家を舞台に繰り広げられる、認知症と振り込め詐欺と家族をモチーフにした…と聞くと、固っ苦しそな印象かもしれませんが、中身はコメディでした。笑
ただ、面白いで終わるのではなく、どこか寂しさも感じる、不思議な気持ちで終わった舞台でした。
感想
途中で、何が本当で何が嘘なのか分からなくなったのですが、もともと芝居は嘘を本当のことのようにやっているものだから、そこも相まって、余計に複雑になりそうなところを、面白おかしく持っていっていたので、楽しく観ることができました。
これぞリアルな芝居
序盤、二人のおじいさんたちが話すシーンから始まるのですが、気づいたら寝ていました。(私が…)
それだけ聞くと、なんだ、退屈な話だったのかと思うかもしれませんが、本当に退屈だったんだと思います。笑
観劇する時は、どうしても、(これから何が起こるのかな!)と何か大きな期待を抱いて観てしまいがちだった自分にとっては、衝撃でした。
だって、芝居なんだけど、本当にそこでおじいさん二人が加山雄三やらの話で楽しそうに話していただけだったから。
芝居だけどリアルな空間が、この序盤で創られていたんだなと、後になって気づきました。
そこから、他の登場人物が出てきて(ハッと目が覚めて)からは、次はどんな人が来るのか、何が起こるのかなどと、勝手な期待を持つことなく、認知症の人たちの日常をただ覗き見していたような感覚でした。はじめての感覚。
個性的なキャラ
詐欺師のキャラが、都会から来ていただけに、相対的に他のキャラよりもパンチが効いていて、なおかつコミカルで面白かった。
そのうえで、最後の方の、その詐欺師も若年性アルツハイマーだったという告白も衝撃でした。それも本当か嘘か分からなかったのですが、登場人物が全員認知症らしいので、本当なのでしょう。
他の登場人物もリアルにご年配で長年の実力ある役者さんも多かったようで、余計な情報なく気楽に観ることができました。
アフタートークにて
終演後に、演出の平田オリザさんと作者の髙山さなえさんによる、アフタートークもありました。
作品について
作者である髙山さんのご実家、長野県の田舎を舞台に、認知症だった髙山さんの祖母との関わりを手掛かりに作られました。
自身が大の高校野球好きということもあり、話の中に高校野球要素も肝として入っていました。
演出について
自分の作品以外の作品を演出するのは、20年ぶりくらいのことだったそうです。かなりレア?!
逆に、それだけこの作品を気に入ったのだなとも思いました。
平田オリザといえばこれ!というような演出があるようで、それが…
同時多発会話
平田オリザさん自らが⦅お家芸⦆とも言っていた、この同時多発会話。
一つのシーンで、複数の会話が同時に展開されていくというもの。今回の作品でも、1ヶ所それがありました。
観客からの感想で、どっちを聞いていいのか分からなかったと(私も一生懸命2つとも聞き取ろうと頑張った)でた問題のシーン。
実は、作者の髙山さんの母が1番喜ぶであろうとした、あずさ2号についての会話のシーン。
演出家からすると、地元長野では盛り上がるかもしれないが、地方公演をするにあたって、あまりにも長いし、あずさ2号が分からない人には分からないという理由でカット…とまではいかなかったが、同時多発会話の演出によって、その会話を裏で流すことによって、時間的に削られたということでした。
観ている人に伝わりやすいように…なるほど。これが演出か。
舞台美術
質問で出てきたので、舞台美術の庭?の木についても話されていました。
流木マニアとして知られているという、杉山至さん。まるで本物の木のような流木が、左右にそれぞれ1本ずつ立てられていました。
質問の内容としては、季節は夏の話なのに、木に葉っぱがないのはなぜか。というもの。そこまで気にならなかったのだが、回答を聞いて納得。
平田さん曰く、舞台上は真ん中が舞台上でのリアルの中心とし、1番細かく作られているが、その中心から舞台袖に向けて、放物線上に非現実的な空間に変わっていくようにしているそうです。
その理屈でいうと、舞台の両脇にあった木に葉っぱがなくても理にかなってるなと。さすが。
公演約2時間に続いて、30分ほどのアフタートークも、とても勉強になりました。
気になる方は、ぜひ劇場へ!
これが当日券(3000円)もあって、高校生以下は1000円とか破格過ぎます。もっといろんな方にも届いてほしい。そんな作品でした。
もっと書きたかったことあるような気もするが、とりあえずここまで。
今後も、香川、三重と公演をするそうなので、気になった方はぜひ!
と思っていましたが、投稿未遂の間に終わっちゃいましたね…
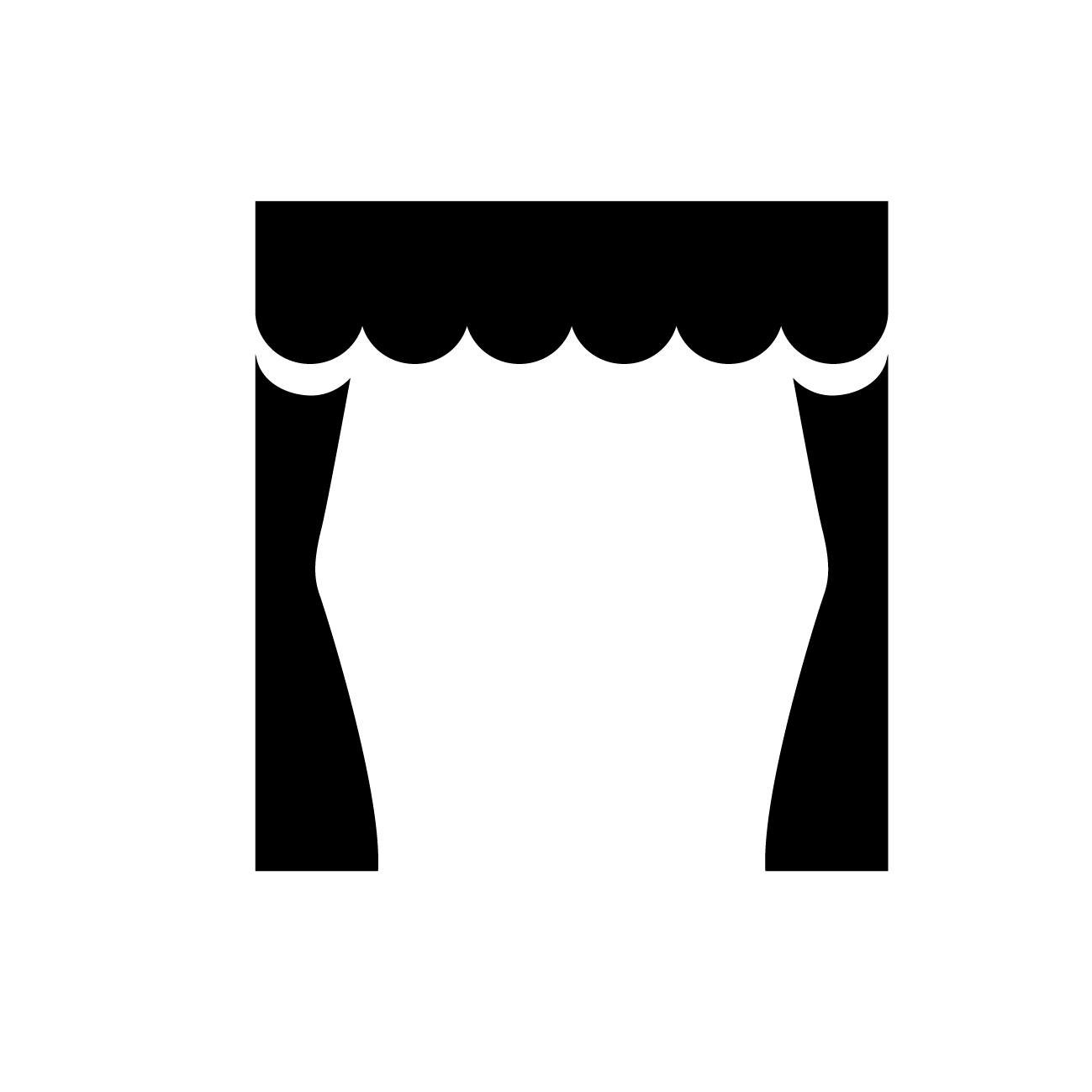
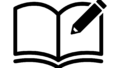
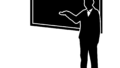
コメント