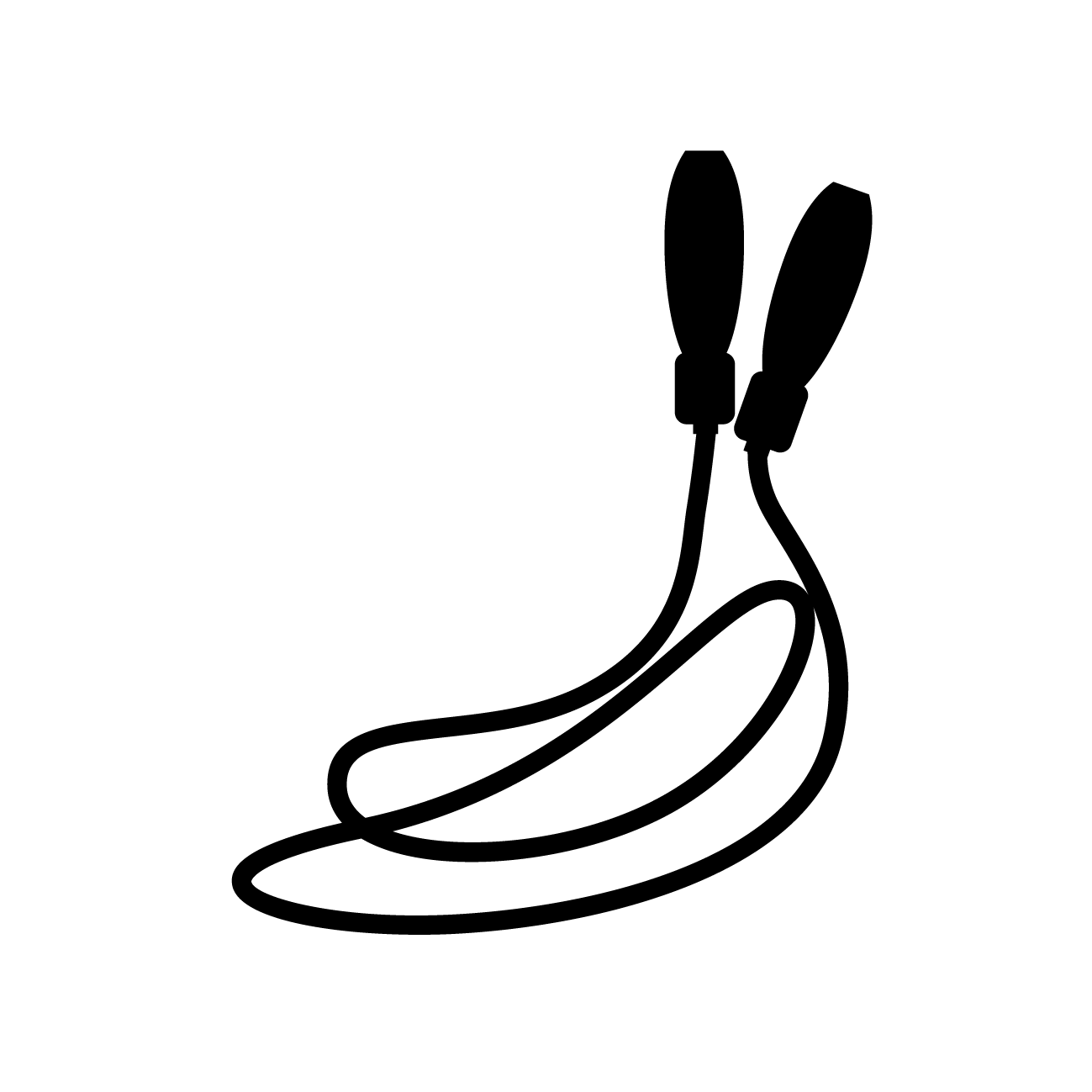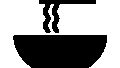様々な切り口から構成力のお話を、私の経験からお話させていただきます。
第2回目は運動会の団体演技。
ここ何年か、団体演技を任せていただくことが多く、年々自分の中での積み上げができたと実感がありました。
どのように組み立てていくのか、近年続いているリズムなわの演技から紐解いていこうと思います。
何から決める?
まずはここ。まっさらな状態から始めの点を打つところ。
曲?手具?それともテーマ?
自分の経験上、手具から決まることがほとんどです。
本当はしっかりと子どもの実態に合わせて、テーマやめあてを決めることがいいのでしょうが…
そこらへんは担任としてクラスを持つほうが考えやすいなと思ったりもします。
あと、テーマやめあては後からついてくることもある。
勤務校では、4年生は毎年リズムなわと決まっているので、何か縛りがあるのも悪くないなと思います。迷わなくていいので!
流行りの曲を選ぶのもよし、持たせたい手具から選ぶもよし、このスタート地点は好みが出るところでもあるなと思います。
一つ決まれば…
何か一つ決まれば、二つ目は意外と決まるのが早くなっていくなと感じます。
リズムなわであれば、跳びやすい速さの曲。
BPM128くらいが、クラブミュージックなどで流れる曲も多く、飛び跳ねやすい印象ですが、なわの場合、それより少し速いとスピード感が出て曲に乗りやすい印象もあります。
逆に遅いと合わせにくい。
そういう意味では、曲の速さはかなり大事。
極端に遅かったり、速かったりすれば、リズムに合わす以外の表現方法もあり。
他の手具だと、その手具のイメージにあった曲。あと動きやすい速さ。
曲は、練習中何度も耳にすることを考えると、自分の好きな曲、アーティストから選ぶのもありかと思います。
しかし、知らない、あまり聞かない曲でも何度も聞くうちに気に入ってくるのも面白いところ。
一生懸命その曲に向き合うと、愛着出てきますよね!
曲が決まっていれば、その曲のイメージにあった手具。とくに色!
手具はなるべく体の一部として大きく見せれるものが、低学年ほど自分を大きく見せて表現できるので私は好みます。
テーマなどは合わせて曲、手具のどちらかが決まることが多そう。どちらか決まればあとは…
演技構成
テーマ、曲、手具等が決まれば、いよいよ演技構成へ。
ここで1番気をつけていることは、
覚えることはなるべく少なく!
パターンに分けても、その数が多すぎると覚えるのが大変、どこで何をするのかごっちゃになる、など
基本的に、曲のAメロ、Bメロ、サビの大きく分けて3つの塊で考えて、曲のその部分での動きは固定してしまう。
これで、動きと音楽(耳)が連動して覚えやすいし、覚えることも少なくなる!
言い方を変えると、曲の構成をもとに、シンプルに考える!これにつきます。
あとは、その曲にあった動きであるかどうか。
そのために、私はまずは曲を聞きまくります。
(毎年、年間で1番聴いた曲の1位は運動会の曲…)
聞いていく中で、ここの部分はこうしたいな、ああしたいなというのが出てくるので、あとはそこの前後をうまくつなぎながら、曲の中の塊を考える。
どんな動きが合うのかは、感覚的な部分になってくるので、言葉ではなかなか表せないのが痛いところ…
ただ、繰り返しやることでハマってくることも。
伝え方
初めはまず、1番多いサビの部分から。
一度そこが伝わると、曲を流してサビになれば、自然と練習をし始めることが多いです。
子どもたちが曲を知らなかっても、サビととらえることができること。曲をよく聴いているなと感心します。
あとは、サビから順に、
・同じ部分が多いところ(Aメロ、Bメロ)
・その他の部分(Cメロ、前奏、間奏、後奏など)
・体形移動
完成!
これからの団体演技
ここからは構成力とは少し話がズレますが…
毎年運動会がある中で、ふと思うことがありました。
これって、先生の自己満足じゃ…?
好きな(?)曲を選び、考えたものを伝えて練習させて発表。
ここから子どもたちが学ぶことは?
もちろん、リズム感や身体能力の向上、目標に向けての積み上げ、達成感などはあると思います。
ただ、受け身になりすぎていないか。
(これは他の授業全般でも言える時もあるのではないか。)
そこで、今年度は子どもたちが中心となって作るれるように投げかけてみました。
子どもたちが作る団体演技
※2024年度の取り組みです。
・曲、手具はこちらで決める。
とくに曲は速さが違うだけで後に大きく響くので。ただ、いくつか選択肢を与えられるとなお良かったと反省。
・構成まで考える。具体的な中身は子どもに。
・中心となって決めるメンバーを決める。
全員で意見を出すと時間もかかってまとめるのも大変なので、有志の中からリーダーを決め、休み時間を使って考えてもらいました。
ポイントは得意不得意関係なく、なりたいやりたい気持ちを尊重すること。立候補が多い時はくじで決める。ただし、リーダーは代表者。リーダーだけが頑張るのではなく、あくまでみんなで作る。
具体的には
・みんなから改善策や意見をもらう
・教え合いながら練習する
など
今回は初めてだったので、どうしても今までの自分ならもっとああしたらこうしたらっていう気持ちが出てきていたが、そこはグッと堪える。我慢!
結果、子どもたちはとても満足しているように見えたし、そういった感想文もあった。
自分の中では満足感はなかったが、それでいいのだと思う。なるべく大人の都合に付き合わせてしまわないように…
ただし、この結果は土台となる構成がしっかりできていたからこそ!
そこは、自分の構成力を称えてもいいのではないでしょうか?よし、満足。
構成力とは
大枠ができていると、見通しをもってできるし、大半出来上がったような安心感も。
と言いながらも、第3回のテーマは決まっておらず、こちらの構成力は??と、なんとも矛盾した企画に…
次回もお楽しみに!