先日の研修レポート。雲雀丘学園小学校にて。
もともと公立の学校だったとか。知らなかった。
ロイロノート主催の豪華講師陣が集まる、仕事納めには勿体無いほどの研修会でした。
最先端の最先端
敬愛小学校の龍校長による基調講演。
これがこの日の9割、もはやそれ以上といっても過言ではない貴重な時間でした。
10年前には1人一台タブレットを導入し、コロナで休校になった翌週からオンライン授業を導入したという、先の先を行っていたという学校。
というか、先の先を行っていたのは校長。
ICT機器の活用、時代の先読みをしていた人は、少ないだろうが他にもいたのは間違いないと思います。
ただ、こういった方が校長に就くことによって、学校の船頭に立ち、周りとは違うことを貫き通してやっていったと言う事実、事例が他にはないのではないかと思う。
少し話は変わりますが、夏の研修にて。
関西にはまだない、学校劇部会に参加させていただきました。
そこで、今年度より校長になられた先生がいたのですが、校長という立場になられて、学校全体に自らが授業をする形で、演劇教育の時間を設けたそうです。
そう、結局は校長が理解を持って動かないと、学校全体で動いていくことができないのです。
年齢云々の問題も少なからずあると思いますが、いついかなる年代、時代になっても、新しいものに目を向け続け、スポンジの用に吸収し続ける精神を忘れないようにしたいものです。
ちなみに…
龍校長によると、次の時代に合った新しい形も用意し始めているとか。
私の理解の範疇を超えていますが、そこで
おお、すごい。
と大谷翔平を見ているような気持ちでいてはいけないなと、自分も教育に関わる立場として、自分なりの新しいスタイルを求めていきたいものです。
ロイロノート
本題はロイロノートの研修ということで、その後は各講師による、各教科ごとの活用事例などの研修。
理科
初めはノートルダム学院小学校の梅下先生のところへ。
私自身、今年から初めて理科の授業を受け持つこともあり、以前のノートルダムの研修でも、少し授業を覗かせていただきました。
最後の宝仙の吉金先生スペシャル対談でも、話していましたが、基本的には実物を使った実験の時間をたっぷりとってあげたいということ。
それ以外の時間で、ロイロノートを活用し、時短、共有、記録の継続などに繋げるという。
やはり1番気になったのは、バーチャル理科室。
ロイロノートの共有ノート上で、周りの子の考えていることを見に行けたり、全体で共有できたりするというもの。
私の学校でも、それを取り入れている先輩がいるので、参考にしつつ、授業で取り入れてみようと思います。
算数
もう一つは、樋口万太郎先生の講演へ。
他校での実践事例を実際に体験しながら、お話しいただきました。
ポイントになったと思ったのが、デジタル教材。
自分もロイロノートの機能を活用したゲームを作成したことがありますが、まだまだ使いようによっては、ロイロの活用方法が沢山ありそうだなと感じました。
とくに、数を要する教具を、うまくデジタル化、活用できたらと思いました。
後もう一つは、今実践中とおっしゃっていた、まとめを次の授業へつなげていく方法。
算数ほど、前時までの既習事項を活用する授業はないことを考えると、積み重ねれば積み重ねるほど、個人の知識、力として残していけるなと思いました。
新年、3学期に向けて
さらには来年度以降に向けて、自分だけではなく、学校として、大きな課題が見えた研修でした。
龍校長の話にもありましたが、
「学ぶことは、真似ること」
まずは色んなことを真似るところから、
そこからは
「守・破・離」
ですね。
今年は、例年よりも多くの研修に参加することができましたが、どこかしら繋がっている?む
むしろ、自分で繋げていかなければならないと感じました。
まあ、まずは冬休み、しっかり休もうと思います。
仕事とプライベート、しっかり分けることも大事!!
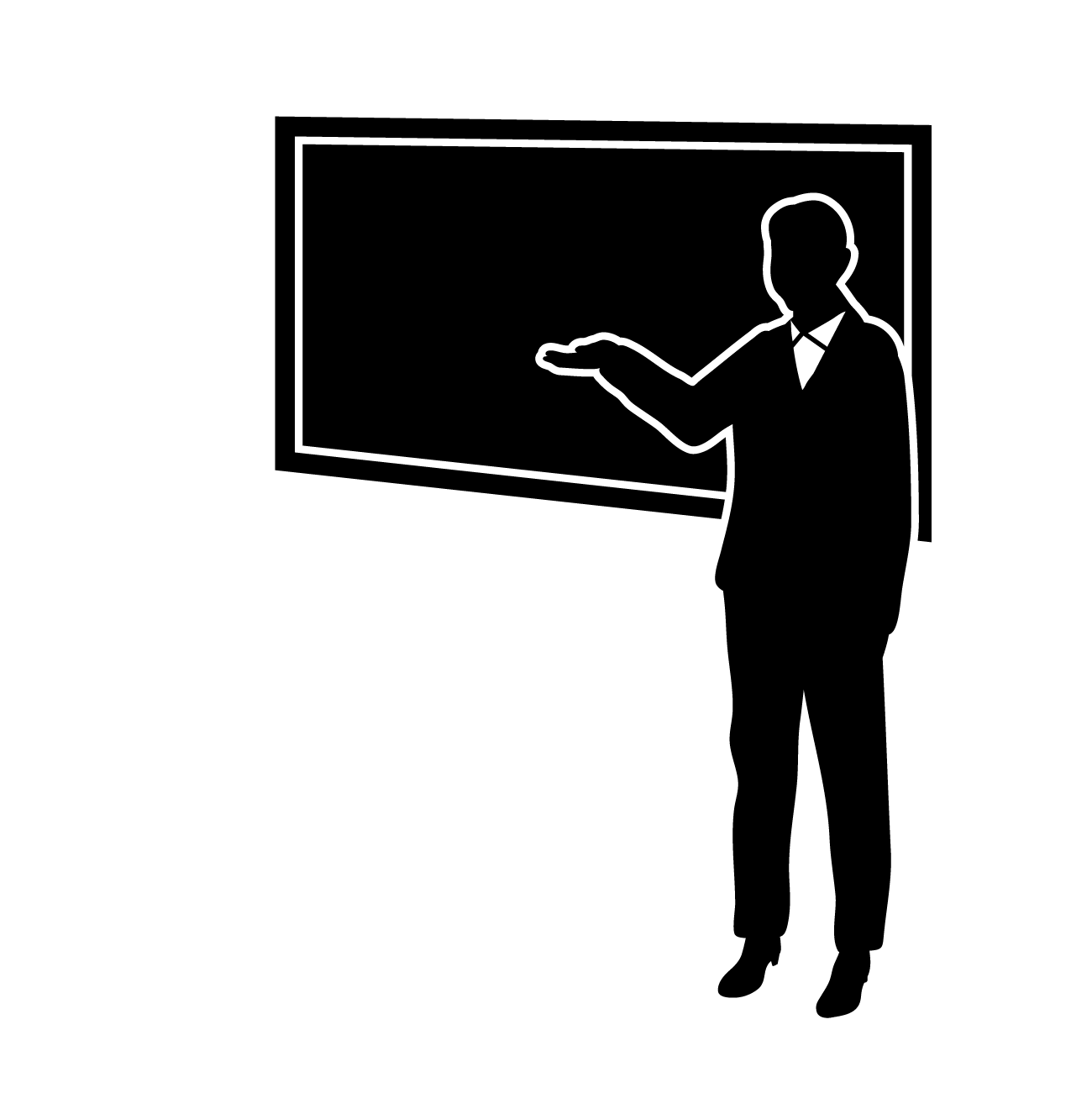
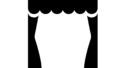
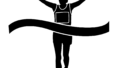
コメント